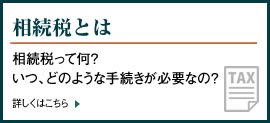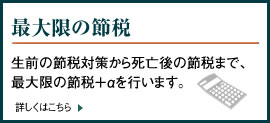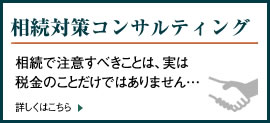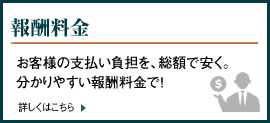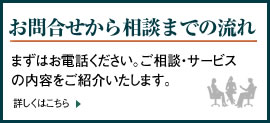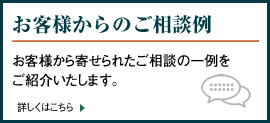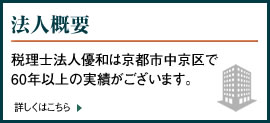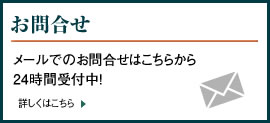お知らせ

相続税の障害者控除
今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。
① 相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
② 法定相続人であること
③ 障害者であること
また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。
控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。
【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円
その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無はことなるため、
しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。
相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。
小規模宅地等の特例の見直し
平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について
小規模宅地等の特例の要件が見直されることとなりました。
一つ目は.貸付事業用宅地等の適用要件の見直しです
被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが問題視され、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることとなりました。ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。
二つ目は三年内の特定居住用宅地等の特例の見直しです。
特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等の居住の用に供している宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から330平方メートルまで80%減額される制度です。この一定の要件のうち、いわゆる「3年内家なき子」というものが見直しとなります。従来の「3年内家なき子」の要件とは以下の三つです。
(1) 被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。
(2) 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。
(3) 当該宅地を申告期限まで保有していること。
上記について、自宅を親族等に譲渡することにより「3年内家なき子」の要件を満たすものとして申告するケースが問題視されたことから、次に掲げる者が「3年内家なき子」から除外されることとなりました。
(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者
(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
少しわかりやすく記載すると
(1)は「自分自身が持ち家を持っていなくても、自分の親族が持っている家に住んでいたり
自分が経営している会社が持っている家に住んでいる場合」は除外となります。
(2)は「持ち家のある相続人が、形式的に持ち家を親族等に売却し、そのままその家に住み続けたり、賃貸して住んでいる場合」は除外となります。
今回の改正で結局どのような場合に家なき子特例が使えるのかというと
単純に「相続の開始前に3年以上賃貸暮らしをしていた別居親族」となりそうです。
該当する宅地をお持ちの方や、相続についてお困りの方、
他にもお聞きになりたいことがございましたら、税理士法人優和までお気軽にご連絡ください。
確定申告後のご相談
今年も確定申告が無事終わりました。
その際に、相続について不安を持たれている方も多くいらっしゃり、
相続税の簡易試算をご依頼いただくお客様もおられました。
各御家庭ごとにご都合もあるかと思います。
今一度、ご不安な点解決されてみれはいかがでしょうか?
相続税対策 死亡保険金について
税理士法人優和では、
しっかりとヒアリングをさせていただき
簡易試算をさせていただいております。
いざという時のため、
対策方法の提案をさせていただきますので、
お気軽にご相談くださいませ。
その中で一つ、ご存知の方も多いかとおもわれますが、
死亡保険金の非課税という税制上の特典があります。
その非課税枠は
500万円×法定相続人の数 となります。
また、保険金の被保険者や受取者が誰かによって、申告する税金の種類も変わりますので、
保険のご契約を検討されている方は、保険会社にご確認ください。
保険についても当社では保険会社と提携させていただいておりますので、
簡易試算も含め、保険内容もご相談いただけます。
相続税に強い京都の税理士法人
相続税は亡くなられた方(被相続人)の財産について相続する人(相続人)に対して課税されます。
税額はどの税理士がやっても同じなはずですが、実際はそうではありません。
税理士法人優和は京都で長年の実績と経験により、
出来る限りの節税を提案させていただいています。
税額は少なく報酬は適正にをモットーにお客様に喜んで頂いています。
さらにお客様1人1人にあった提案を行うため、相続税に強い税理士法人と言われています。
相続について心配という方は、出来るだけ早い段階でまずご相談下さい。
大廃業時代に対応する税制を拡充・創設
経済産業省によると、中小経営者で最も多い年齢層は2015年時点で
65歳~69歳で平均引退年齢は70歳です。
今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)になるにもかかわらず、
その半数以上が事業承継の準備を終えていません。
廃業を放置すれば2025年までの累計で約650万人の雇用と
約22兆円に上る国内総生産(GDP)が失われる恐れがあります。
経営者の年齢が若いと売上高が増加する傾向なることから、
次世代への経営の引継ぎは、地域経済・雇用の維持・活性化に繋がります。
平成30年度税制改正の経済産業省の要望書では、
多様な経営の引継ぎに応じた税負担の軽減措置を講ずることより、
事業承継を加速させる要望が上げられています。
■中小企業・小規模事業者の事業継続を促進するための要望内容(経済産業省)
⑴贈与・相続(拡充)
親族や従業員等に株式等を贈与・相続する場合の事業承継税制の抜本的拡充宇
⑵売却・M&A(創設)
他企業や親族外経営者等に経営を引き継ぐ場合の譲渡益に係る税負担軽減、
登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減
⑶ファンドへの売却(創設)
ファンドを経由して事業承継を行う場合に税負担の軽減
■事業承継対策の早期の着手が重要
中小企業庁の調査で、直近10年間における経営者の親族内承継の割合が急減し、
従業員や社外の第三者といった親族外承継が6割超に達したと報告されました。
税金の負担を軽減して、円滑な事業承継をすすめるためには、事前の綿密な計画と事業承継を
実行する決断が必要となります。
事業承継に関するご心配事があれば出来る限り早めにご相談ください。
最新の情報にもとづき適切なサポートをいたします。
相続税においての節税対策 貸家建付地における賃借割合について
相続税において最もポピュラーな節税対策の一つとして
「賃貸アパート」の建設が挙げられるのではないでしょうか。
アパート建設の際の借入金が債務として相続財産から控除されることで
相続財産を圧縮する効果があり、更にその土地については約2割に評価減、
建物については3割の評価減・・・と、
何だかいいこと尽くめの節税対策のように思えてしまいますが、
ここのところこの「貸家建付地」絡みの節税策について何やら雲行きが怪しくなってきたように感じられます。
そもそも自分の土地の上に建てた建物に賃料を貰って他人を住まわす行為については、
専門的な用語で言うところの「借家権の支配」が及ぶこととなり、
その人を勝手に退去させることはできず、退去してもらうには立退料という費用が発生することとなり、
そのように自分の土地建物について自由な使用が制限されることに対して
財産評価上、評価減という斟酌がなされることとなっております。
しかしながら賃貸集合住宅においては、
常時満室という状態が続くということは地域によっては考えづらく、
築年数が経つほど空室割合が増すほうが一般的なのです。
ここが問題で、相続税における財産評価は相続発生時における時価となっており、
つまり亡くなった日にその部屋に入居者がいない場合、
その部屋については「借地権の支配」が及んでないことから、
その土地及び建物についての評価減を受けられなくなってしまうのです。
ただし、さすがにたまたま亡くなる直前に入居者が退去してしまい、
すぐに新たな入居者が入るケースについては、
入居者がいるとみなして評価減を受けることができるのですが、
その要件として常に賃貸用として募集もしている等の場合、
課税時期前後概ね1か月程度の空室については、
入居者がいるものとして評価減が認められるという国税庁の情報が公開されております。
ここでいつも揉めるのが、「課税時期の前後の例えば1か月程度の空室期間」についての解釈なのです。
平成20年6月の高松国税不服審判所裁決事例では、
空室期間が生じた諸事情も考慮すべきとし、最長1年11か月の空室期間も一時的な空室として認められ
この裁決が一時的な空室の期間についてのジャッジにおいて重要な判断材料となっておりましたが、
ここのところの裁決事例ではその一時的な空室に期間が短くなっており、
とうとう平成29年5月11日の大阪高裁において5か月の空室を長期間と判断される判決が出てしまいました。
このような流れがスタンダードとなってしまうと
課税庁側は金科玉条の如く課税時期前後1か月以上は空室と判断してくることとなるでしょうし、
納税者側としてもこの空室期間についての諸事情を主張しづらくなってしまうのではないでしょうか。
例えば、10室のうち8室が空室というアパートの場合、
20%の評価減がたった4%の評価減となってしまうのです。
昨今の賃貸アパートの建設ブームを考えると今後も築年数が経てば経つほど、
空室が増える可能性は高くなり、せっかく節税対策として建てたアパートも
建設当初に想定していた評価減を十分に受けられなくなるという事態が
今後増々増えてくるのではないでしょうか。
広大地評価において今年中に「やっておくべきこと」と「やってはいけないこと」
もう、皆さん周知のことかと思いますが平成30年1月1日以降現行の広大地の評価(財産評価基本通達24-4)が廃止され、地積規模の大きな宅地の評価が新設(新評価通達20-2、以降の通達番号は1項ずつ後退する予定)されることとなる見込みとなりました。
現行の広大地評価は、評価に主観性が多く盛り込まれ鑑定評価やその通達の解釈の相違等の裁決事例の多さからわかる様に納税者側だけでなく課税庁側も相当苦心していたことは想像に難くないところでした。
それだけでなく、市場価額と相続税評価額の差額に着目し、地形のよい広大地を生前に購入し、相続後に売却するといった一種のタワマン節税に似た相続対策が横行していたことも課税庁側とすると苦虫を噛み潰す思いであったこともまた想像に難くないところでした。
このような過去の経緯からしても今回広大地評価の「改正」ではなくわざわざ「廃止」して「新設」するという、この主観性のかたまりだった広大地評価から完全決別したいという課税庁側の強い意気込みすら感じ取れるように思われます。
今回の改正について今年の12月31日までに想定される動きを5つのカテゴリーに区分してみました。
① 現行広大地評価は適用可で新通達は適用不可
② 現行広大地評価は適用可で新通達も適用可
③ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用不可
④ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用可
⑤ 現行広大地評価は適用不可で新通達は適用可
1.2については、今年中に相続時精算課税を利用して広大地評価が適用可能な土地について生前贈与の検討も必要になりそうです。勿論相続時精算課税を利用した場合、その後暦年贈与ができなくなることも考慮する必要はあります。
3については、最悪広大地評価が相続税申告後否認されたとしてもどちらにせよ加算税等の課税のみなので納税者にリスクを説明したうえで通常通り状況によってはチャレンジする価値はありそうです。
問題は4で、仮にチャレンジして失敗した場合加算税等のみならず新通達の評価減についても捨てる結果となることからもあまり可能性が低いようであれば安全策をとって新通達の評価減を選ぶべきかも知れません。
5については問題なく来年までスルー。
新通達の評価については、例えば容積率の条件についても建築基準法52条1項(指定容積率)についてしか謳われてなく、基準容積率や容積率の加重平均については何も触れられておらず対象から外れることが濃厚であることから、これらも年内に贈与するか否かの判定において重要な判断材料となりそうです。
相続税計算時の準確定申告の所得税等について
年の途中でお亡くなりになられた年の所得税の申告のことを準確定申告といいます。
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。
それにより発生した所得税または還付金は相続税の債務または課税対象となります。
また、後期高齢者医療保険料や介護保険料の還付金も相続財産となりますので、 注意が必要です。
弊社では相続税の申告時、申告漏れのないよう、
しっかりヒアリングさせていただきますので、ご安心してご依頼いただけます。